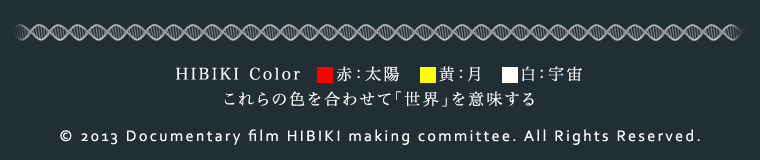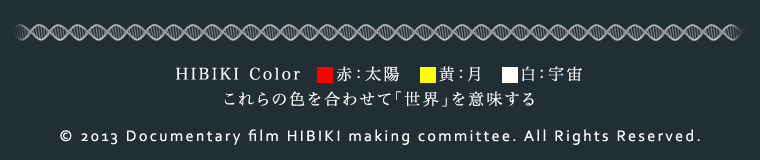サーミは、スカンジナビア半島北部、及びロシア北部コラ半島に至る、ラップランドと呼ばれる地域(ノルウェー、スウェーデン、フィンランドの北欧三国とロシアの四ケ国)に居住する、トナカイ遊牧民として知られる先住民族。
サーミに先祖代々から伝わる叡智は、冬が一年の半分以上を占める、雪と氷に深く閉ざされた厳しい世界で生き抜くためのもの。
命の存在をまるで拒否するかのようなこの北極の地になぜ人が住んでいる?
この質問は、サーミにとって愚問である。
彼らは、先祖代々からこの地に住んでいることに、一切の疑問を持たないのだ。
サーミは、ここにいるべくして、いるに過ぎない。
そして、このような過酷な大自然の中で、サーミと共にいるのが、トナカイである。
サーミを語るにトナカイは欠かせない。
以下、ディレクターズ・ノートから。
==========
【ディレクターズ・ノート:サーミとトナカイ】
現地時間 2018 1.8 22:30
ヨイクの帰り、Einoさんの家で朝目覚め、雪掻きのお手伝い。
しかし、僕が知っているレベルの雪掻きとは桁違い。
重機を総動員して、地平線の向こうまであるんではないかと思うくらいの広いエリアを作業する。
朝まで降り続けた雪は、家の一歩外に出ただけで、腰の高さまで来る。
雪掻きというより、新しい「道作り」のような感覚。
響きの旅は、毎回ホームステイになる。これも不思議。
そして、いつもその御礼に、何かお手伝いさせて頂く。
僕のラッキーアイテムの軍手は、流石に今回の寒さには叶わなかったが、カバンの中に持ち歩いている。
この日の朝の気温は、マイナス22度。
寒いのか、痛いのかよく分からない。
でも、一生懸命にお手伝いさせて頂いた。
それから、Einoさんの息子、Anttiさんがやって来て、ミーティング。
Anttiさんの妹、Hannaさんが、イヴァロのもう少し先の、サーリセルカに住んでいて、トナカイの牧場をやっていると言うので、ご紹介頂き、すぐに出発。
車で、約3時間のスリリングな道のりを滑りながら、夕方になってようやく到着。
 掘っ立て小屋に一泊し、今朝の9時に、待ち合わせ場所に行って、いきなりトナカイのソリのシーンを撮影。 掘っ立て小屋に一泊し、今朝の9時に、待ち合わせ場所に行って、いきなりトナカイのソリのシーンを撮影。
聞くと、カーモス(極夜)明けが近く、まだ地平線の下にあるだろう太陽の真っ赤が、白銀を優しいピンク色に染めていた。
素晴らしいシーンを撮影出来た。
サーミにとって、トナカイはどのような存在か?
それは、アフリカのマサイにとっての牛とは、少し違った。
マサイにとって、牛は神さまからの贈りものであると長老が言った。
では、サーミにとって、トナカイは?
ソリが終わって一息のHannaさんに聞いてみた。
 すると、彼女、まるで愛しい人を見つめるように、優しい笑顔を浮かべて、トナカイにそっとキス。 すると、彼女、まるで愛しい人を見つめるように、優しい笑顔を浮かべて、トナカイにそっとキス。
響きのキャメラがその瞬間を捉えた。
「トナカイは、とても大切な存在。サーミの、お爺ちゃん、お婆ちゃん、先祖代々からずっとそう伝わって来てるのよ。私が小さい頃からずっと一緒。家族なの」
と、質問に答えるHannaさん、とても幸せそう。
僕は、その姿を見て、これ以上の質問を止めた。
僕が「納得する答え」は、もう何の意味もない。
求める者は、求める答え有りきで、聞く。
つまり、その先を自分のイマジネーションの中に「閉じ込める」
ゆえ、どんな答えが返って来ようとも、自身の「解釈」の中に過ぎない。
僕は、ビジュアル(映像)が持つ真の力を信じて疑わない。
Hannaさんが見せる微笑みに、僕はすべてを委ねた。
==========
【ディレクターズ・ノート:響きの舵取り】
現地時間 2018 1.18 07:30
獣医マリアが僕の目の奥をじっと見つめて来る。
 長老の目だ。 長老の目だ。
僕にとっては幾度も経験した目。
相手の魂を見ているのだ。
ほとんど英語になってない僕の発する言葉の真意を見極めるべく。
僕は必死だ。知っている限られた単語をつないで一生懸命に伝えようとする。
いつも思う、通訳がいてくれたらなぁと。
でも、言葉が出来ないからと言って、諦める訳にはいかない。
恥を晒して済むならば、いくらでもそうするし、そうして来た。
とにかく、命掛けで必死なのだ。
目の前にやって来たチャンスは、一度切り。あっという間に過ぎ去ってゆく。
その時にそれに勘づく野生の鼻が必要。
今出来ることのベストを、必死でやる。
それで出来なかったら、神様の答え。そっちじゃないよ、ということだ。
これが、たったひとつの、響きの舵取りなのである。
実にシンプル。
昔、響きのはじめの頃、僕が言っていることは狂ってるし、絶対に成し得ないだろうと言ったある人が、
「まず、少なくとも英語をマスターしてから海外に飛び出したらどうですか? お金も何もない上に、言葉も話せないようでは、ただの夢物語。仮に行けたとしても、どうやってコミュケーションを取るんですか?」
と、僕に言い聞かせた。
全くの正論である。僕は言い返すことも出来ず、その場を後にした。
しかし、昨晩の獣医マリアが僕をまじまじと見つめ、言葉になってない言葉を真剣に聞き、そして、優しい微笑みを浮かべて、即答。
「いいわよ。金曜日の朝にやりましょう」
マリアがこの時に見せた目は、これまでの先住民族の長老たちが僕を見つめるのと同じだった。
確かに言葉は大切。
でも、人にはハートがある。
この世界には、たくさんの言葉や文化、肌の色がある。
でも、僕たちは言葉(思考)を超えて、違いを輝きにし、互いを理解して、愛しあうことが出来る。
響きの旅で学んだこの世界の真理。
ドキュメンタリー映画「響き 〜RHYTHM of DNA〜」のメインコンセプト、響き合う、その実体験である。
明日、獣医マリアのインタビューを撮り、そのあとトナカイの診療のシーンをタイミングが合えば、別の日に行う。
マリアは野生のトナカイの専門家で、この冬の季節は、難しいようだ。
しかし、少し考えてみると仰って下さったので、それに委ねよう。
==========
【ディレクターズ・ノート:響きスタイル】
現地時間 2018 1.18 22:30
響きスタイル健在。
今日の余りにも想定外過ぎる出来事には、さすがの僕も、うなだれた。
最近、出来るだけ「奇跡」という言葉を使わずして、淡々と発信して来たが、やっぱりこの言葉しか今日の出来事を表現出来ないだろう。
早朝の6時過ぎ、獣医マリアから連絡が入る。
「今日、急病のトナカイがいて診察に行くことになったけれど、あなたも来るかい?」
「え!?」
前日のミーティングで、冬の間はまず、それはないと、マリアから言われたばかり。
半信半疑で、マリアのクリニックに駆けつけると、
「あなたはとてもラッキーね。昨日、お話しした通りだけれど、この季節、とても珍しいわ。急にトナカイの診察が入ったの。偶々。不思議ね」
「・・・・・」
出た、響きスタイルの奇跡。
昨日の今日。まさか、、、。
僕は明日の金曜日のインタビューが出来るだけでも、大満足だったのだ。
マリアの車に乗せてもらって、マイナス25度の中で、トナカイの診察。
 すごいシーンが撮れた。 すごいシーンが撮れた。
昨年夏、アフリカ・ケニアでの、かんべ先生のマサイの牛の診察とオーバーラップして来る。
かんべ先生と、マリア、ほとんど同じ動き。
そして、動物を見つめるまなざしもだ。愛に溢れている。
ふぅ、、、響きは完全に僕の範疇を超えている。
毎回の旅に起きるけれど、僕がどんなに遠くを見たって、神様はそれをいつの時も遥かに超えて来る。
諦めてはいるけれど、でも、やっぱり想定外過ぎる。
マリアのトナカイを見つめる目は、遠い子孫に向かっていた。
==========
【ディレクターズ・ノート:カリーナとトナカイ飼いユンの夢】
現地時間 2018 2.6 01:00
ノルウェー・カラショク。
イナリのサーミ・フィルムフェスティバルのミッドナイトパーティで出会った、カリーナが導いてくれた。
フィンランドのサーミと言えば、イナリ。
そして、ノルウェーは、カラショクである。
この地には、サーミの議会があって、彼らの文化・政治の中心拠点でもある。
一度、ノルウェー・トロムソでアプローチしてみたが、その時はうまく行かず。しかし、やっぱりご縁があるのだろう、カラショクのサーミを取材出来た。
 カリーナのお家で、二泊、ホームステイした。 カリーナのお家で、二泊、ホームステイした。
彼女は数々の困難な時を乗り越えて、今に至る。
プライベートな事柄なので、ここでは書けないが、カリーナの深い優しさがどこから来るのか理解出来た。
撮影当日の昨日の朝の気温は、マイナス40度近くあった。
ちなみにこの地の最高記録は、マイナス65度らしい。気温って、どうすればそこまで下がるのだろうと思う。
すべてが凍りつく世界。
金属は素手で触ると皮膚が剥がれてしまう。
朝、カリーナの家の近くのガソリンスタンドで待ち合わせ。
カラショクのトナカイ飼いユン(John Samuel Utsi)が、スノーモービルで僕と彼女を迎えに来てくれた。
今旅、さすがに何度もスノーモービルに乗っているので慣れては来たが、雪深い山の肌を走るのはスリルがある。
木と木の間を風のように駆け抜け、山の頂上にあるとても小さな小屋にたどり着いた。
煖炉に火をつけて、ユンが用意したトナカイの煮込みを食べながら、インタビュー。
ユンは英語が出来ないので、カリーナが通訳してくれた。
途中から、英語の弱い僕を助けて、彼女もユンにインタビューしてくれた。
というのも、前日の夜、カリーナと食事をしながら、ゆっくり時間をかけてコミュニケーションを取ったので、僕が何を聞きたいか、彼女はよく理解していたのだ。
カリーナと僕の、二人三脚のインタビュー、トナカイ飼いの深い世界に触れることが出来た。
最後に、あなたの将来の夢はなんですかと聞いてみた。
「先祖代々から伝わるトナカイとの生活スタイルを、遠い子孫まで繋いでゆきたい」
と、誇り高く、まっすぐに話すユン。
そして、ポケットからスマホを取り出し、画面を見せながら、
「2年前から、GPSをトナカイに付けているので、放牧も少し楽になったよ」
と、笑顔を浮かべるユン。
それから、実際にGPSを辿り、トナカイを探した。
トナカイと一緒にいる時のなんとも言えない幸せそうなユンの表情が、すべてを物語っていた。
この酷寒の地で、トナカイと共に生き抜いて来たサーミの叡智は、ユンの笑顔にある。
素晴らしい。実に素晴らしい。
叡智とは何か?
僕が先住民族に求めて来た答えが、輪郭を表して来た。
叡智とは、その土地に根ざしてある「幸せ」のカタチなのだ。
そして、今を生きる僕たちも「先祖」
僕たちが経験したものを「叡智」にし、次の子孫に伝えてゆくのだ。
時代の流れとともに繰り返される「叡智の創造」こそが、人類の普遍そのものであろう。
 ちなみに、焚き火を前にユンが横たわっている姿勢もサーミ独特のもの。 ちなみに、焚き火を前にユンが横たわっている姿勢もサーミ独特のもの。
酷寒では、焚き火の熱も上に昇らないので、こうして横たわった姿勢でいるとすぐに暖かくなるという。
僕も試してみたが、その通りだった。
「でも、この姿勢、辛くないですか?」
と、聞いてみた。
「いや、僕たちは小さい頃からずっとこうしているから、平気だよ」
と、ユン。
この姿勢も叡智そのものである。
カリーナも、民族衣裳でヨイクを歌ってくれた。
「私たちの本来は自然にある存在すべてに神々を見出す民族。自然への尊敬と畏れからサーミのスピリッツは成り立っている。クリスチャンがこの地に入って来て、私たちの文化の多くが壊れてしまった。でも、まだ取り戻せる。きっと私たちは出来るわよ」
と、カリーナ。
カリーナは、サーミのシャーマンの家系に生まれている。そのDNAの意思の力を見た。 |